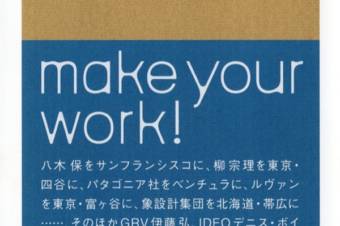まさか、マイクロソフトがSF小説を出すとは!というわけで今週一番シビレたニュースは、マイクロソフト・リサーチが出版したSF短編集「Future Visions」だった。
無料で読めるこのSF短編集は、マイクロソフト・リサーチがSF作家を招いてディスカッションした内容を基に書かれたもので、同研究所の研究を紹介する目的もある。つまり、この書籍自体が広報だということ。広報でSF小説出すとか、やることが洒落てる。
しかも参加しているSF作家はヒューゴー賞やネビュラ賞を受賞した作家ばかりという豪華っぷり。今回は、「自分ならどの作家に頼むだろうか?」と考えてみた。
Contents
グレッグ・イーガン
間違いなく当代随一のハードSF作家。グレッグ・イーガンの著作を完全に理解するには博士号の1つや2つは必要になる。
物理学、数学、コンピューターサイエンスなど、ありとあらゆる分野の知識を煮しめ、私たちが普段当たり前としている事柄 – 幸せ、自己、時間、親子 – を違う目線で感覚させてくれる。
お話の技術的な側面はこれでもかというぐらいハードなのにも関わらず、それによって語られるものが意外と身近な話題だったりするところがグレッグ・イーガンの魅力だ。
ディアスポラは、太陽系全域にネットが張り巡らされ、人類の殆どが肉体を捨てたた未来が舞台で、純粋に電子的な存在「ヤチマ」による宇宙規模の冒険が描かれる、グレッグ・イーガン作品の中でも飛び抜けて空間的・時間的スケールの大きなハードSFの頂点。
しあわせの理由は、グレッグ・イーガンの入門編として最適だろう。技術的な下敷きのハードさを少し抑え、日常的な話題を違う視点から捉えることに注力している。
アーサー・C・クラーク
説明の必要もないほどの偉人。人類を超越した存在を描いた小説が多く、アーサー・C・クラーク自身が超越者なのではないかと思うほど、一度読み始めると止まらない。
神のような技術力を持つ、人類を超越した存在の描き方の卓越はもちろんのこと、科学技術描写のディテールにも舌を巻く。
2001年宇宙の旅はアーサー・C・クラークがスタンリー・キューブリックが協同して劇場版と小説版を制作した、言わずと知れた名作。劇場版2001年宇宙の旅は、映像と音楽の素晴らしさが語られることが多いけれど、小説版はアーサー・C・クラーク一流の技術描写の巧さが随所に見られ、「男の子」がワクワクする作品に仕上がっている。
テッド・チャン
非常に著作が少ないにも関わらず、多くのSF賞を受賞している作家。そこんところが格好いいね。
読者を置き去りにせず、気づけば作品世界の中で暮らしているような錯覚を与える技術や設定描写のお点前は、テッド・チャンがテクニカルライターを本業としてしているからだろうか。理系の科目が苦手だったという人でも問題なく読み進んでいける書き方は、「フェルマーの最終定理」で数学を明朗に描いたサイモン・シンに通じる。
「あなたの人生の物語」は、テッド・チャン唯一の短編集。神々の世界を目指したバビロンの塔のお話に、技術的な信頼性を与えた「バビロンの塔」、宗教に対する辛辣な批判を下敷きにした「地獄とは神の不在なり」、美人か不細工かという価値観を無くすことを実現した社会に生きる大学生たちをインタビューした「顔の美醜について」など、テッド・チャンが多作だったらと本気で残念に感じさせる名作ばかりが収録されている。
ダグラス・アダムズ
SFというジャンルは、その下にまた無数のジャンルを抱えている。その中にあって、抱腹絶倒SF – スラップスティックSF – の大家がこの方 ダグラス・アダムズだ。
イギリスの脚本家や作家の手になるお話によくある、惚けているのか真剣なのか曖昧なコメディセンスはダグラス・アダムズも持ち合わせていて、荒唐無稽とはこの事だ!と言わんばかりのストーリー展開にも関わらず読者を掴んで離さないのは、そういうセンスが活きているから。
銀河ヒッチハイクガイドは、そんなダグラス・アダムズの代表作。「生命、宇宙、そして万物についての究極の疑問の答え」が42であったり、銀河を走る高速道路の建設の邪魔になった地球がいとも簡単に破壊されたりと、無茶苦茶なお話が続くが、魔法のように辻褄を合わせる(合っているように見せる)力は、さすがダグラスといったところ。ちなみに42という数字は後世の多くの作品で使われていて、SF映画なんかを見ているとよく出てくる。
ハーラン・エリスン
残念ながら、日本では二作品しか邦訳されていないアメリカのSF作家。その理由はなんだろう?と考えてみると、短編集「世界の中心で愛を叫んだけもの」が浮かぶ。
この本に収録されている表題作では、暴力と社会批判が匂い立ち、それとハイコントラストを為して愛が描かれている。そこに書かれた社会批判とは、冷戦時代のアメリカを念頭に置くとピンと来やすいものばかりなのだけれど、それが果たして日本人のマジョリティに響くかというと疑問が残る。
作品の訴えみたいなものを差し引くと、後に残るのは、作品の難解な設定・描写である。ゴミ収集車や下水路のように、暴力という目を背けたいものを知らぬ間に知らない場所へ捨ててくれる”装置”があり、暴力が取り除かれた世界は平和に満ちていて、暴力を排出された側は地獄を味わうという設定なのだけれど、説明が無いからとにかく分かりにくい。作品世界、あるいはそこで語られるギミックが分かりにくければ分かりにくいほど良いというSFファンもいるけれど、これではどうしたって大衆受けするわけがない。そこが、ハーラン・エリスンが日本でヒットしていない理由だろうか。
だけれども、どうしてこの作家の著作に惹かれるのだろう? 特にこの難解な短編に。そう考えて、もう一枚、この難解さというベールを剥いでみた。後に残ったのは、”愛”である。
ハーラン・エリスンの考える愛とは決して綺麗事ではなく、美も醜も混じりあったもので、どこか非常にハードボイルドな匂いを感じ取れる。その独特な愛の形は、他の短編でも描かれていて、ハーラン・エリスン独自の思想として一貫している。是非、長編でじっくりとその愛の考察を味わってみたいものだ。
安部公房
「砂の女」で、不条理かつ実存主義的な世界を描き、すっかり文豪として認められた安部公房をSF作家として推すと、「おや」と思うかもしれないけれど、ハヤカワSFコンテストの選考委員を第1回目から3回務めたり、黎明期のSF作家と親交があったりする、れっきとしたSFの人。
第四間氷期は、「予言機械」なる未来予知ができる人工知能が開発され、試しにごく一般的な中年男性の未来を予知させるところが前段となっている。この部分の、人工知能を開発した大学研究室での学生たちの会話や、教授のくたびれた感じ、中年男性にまつわるミステリーライクな部分などが総合して醸す雰囲気がとても良い。「うる星やつら2 ビューティフル・ドリーマー」の学園祭前夜のシーンにも共通したあの感じ。
思えば、安部公房の作になる「砂の女」では、「実存は本質に先立つ」という実存主義の前提条件と、だからこそ「本質は我々が選べる」ことの自由による不安と喜びが描かれていたけれど、この第四間氷河期では、本来は未来にあって見えないはずの本質が、人工知能の未来予知によって見えるようになったとき、実存主義者がどう振る舞うかといった実験だと考えると面白い。
アンディ・ウィアー
SF界きってのイマドキっ子である。
1972年生まれのアンディ・ウィアーが自身のWebサイトで連載していた「火星の人」の人気に火が付き、2011年にkindleで電子書籍として出版すると、3万5千回ものダウンロードを達成し、2014年には日本でも文庫版が発売され、続く2015年、監督をリドリー・スコット、主演はマット・デイモンが務めて「The Martian (邦題: オデッセイ)」として映画化された、イマドキ・シンデレラ・ボーイ。
間違いなく今一番ホットな作家の始まりがWebサイトで、しかも初の書籍化が電子書籍だったなんて、つくづく”イマドキ”な道を歩いて成功したというわけ。
今のところ、著作は火星の人のみ。元から日本語で書かれたんじゃないの?と思うぐらい翻訳が巧いため非常に読みやすい。
火星に取り残された宇宙飛行士が31日間分の物資で1年半生き延びるが、こう書くと、凄絶なサバイバルものに思われるかもしれない。しかし主人公のマーク・ワトニーがユーモア溢れる性格に描かれているおかげで、悲壮感は全く無く、ハードな技術描写とコメディ部分が奇跡のようなバランスで1つの作品として結実している。
そういえば、ゼロ・グラビティのジョージ・クルーニーもやたらとユーモアに溢れていて、生死を分ける状況で冗談を言っていたな。そういう精神のタフさも宇宙飛行士になるための条件なのかしらん。
ウィリアム・ギブスン
1984年にウィリアム・ギブスンが著した「ニューロマンサー」は、サイバーパンクSFの原点にして頂点という月並みな文句しか出ないほど、ぐうの根も出ないほど魅力的な作品だ。
日本なんだか中国なんだかわからないアジア風の薄汚れた街並みや、泥水と止まない雨の湿度、ギンギラギンに輝くネオンなどからなる粗野と、最新デバイスの取り合わせ……。
ニューロマンサーはこうした最先端で猥雑な街を舞台としているが、「アンドロイドは電気羊の夢を見るか?」の劇場版である「ブレードランナー」でも共通して描かれたこの強烈なアジアの「どこか」は、後の数々のSF作品でリフレインされてきた。
まだコンピューターでさえ一般的でなかった時代にウィリアム・ギブスンが描いた電脳世界は、バーチャルリアリティとインターネットが組み合わさったような、現代でも実現できていない世界だ。
果たして、この描写を当時の人たちは理解できていたのだろうか?と思う。私たちは、攻殻機動隊やマトリックスによって、電脳世界がどういうものか視覚的に知っている。ところが、これが文字だけとなると理解に無茶が出てきても仕方がない。
「ワケがわからないけど、何かすごい」とは、ニューロマンサーに対してよく言われることだけれど、それだけ時代の先の先を行っていたということだろう。
そんな作品を作ったウィリアム・ギブスンは、さぞやコンピューターサイエンスに詳しいのかと思いきや、この作品の執筆中はコンピューターを持っておらず、ニューロマンサーで儲けた金で初めて買って、そのショボさに愕然としたという逸話がある。
ブライアン・W・オールディス
エスクァイアの記者によるインタビューで、ブライアン・W・オールディスが、「スターウォーズのフォースってのは拳銃のことだろ?」と言っていたのにはピカリと色んな糸が繋がる思いだった。
確かに、フォースを拳銃に置き換えれば、何故ヒーロー側も悪役側もフォースを使えるのか、フォースが戦闘以外に役立ちそうにないのはどうしてか、結局フォースって何だ?みたいなところが一挙に解決する。
あれは、アメリカ人にとっての拳銃であり、単なる武器なのにも関わらず、使う者次第でどうのこうのという無理くりな論理が展開される。だから「フォースって結局なんですのん?」となるわけだ。
世界で最も愛されているSF映画「スターウォーズ」に対して鋭い意見を持つブライアン・W・オールディスによる「地球の長い午後」は、他のSF作品と毛色がハッキリ異なる。それは、この作品に科学技術が登場しない点にある。他のSF作品が、多かれ少なかれ、科学技術を小道具として使うのに対し、この作品では、技術が失われ、原始的に暮らす人類が描かれている。
多くの人が考えるSF的なるものを排除するという、トリックに対するトリックみたいなものだけが、しかしながらこの作品の魅力ではない。遥か未来の地球で暮らす、存分に成長・進化を遂げた生物たちの営みが、ある種神話的魅力を放っているのだ。本当にこんな世界があるのかも、と思わせるほど動物や植物、地理のディティールの細かさに支えられて、知能も技術も失った人類が生き延びる様が、サバイバルの緊張感と並んでどこか広い平和を纏っていて、それはさながら”神話”だなと思う。
フィリップ・K・ディック
死後、数々の作品が映画化され、わけても「アンドロイドは電気羊の夢を見るか?」の映画版「ブレードランナー」は、退廃的かつ先鋭的な未来世界が後のSF作品に大きな影響を与えたのみならず、ギリシャ神話のオイディプスにキリストをミックスした神話的メタファーの散りばめられた、何度鑑賞しても発見のある名作として世に名を残している。
「ブレードランナー」が神秘的モチーフによって鑑賞者へ視覚的に考察を促す一方、原作である「アンドロイドは電気羊の夢を見るか?」は、アンドロイドという存在を通して”心”にフォーカスしている。
それは、心を巡る実験といえる。人間と瓜二つの存在であるアンドロイドを用意し、アンドロイドにも”心”が芽生えるのか?という実験だ。
そして、もしアンドロイドにも心が生まれたなら、心が人間だけのものではないということになる。この結果を拡大すれば、人間以外の存在(動物、植物、機械)にも心がある可能性が現れる。
それは、「心があるから人間だ」という論理を破壊し、すなわち「人間ってなんだ?」という不安にも繋がっていく。
この底なし沼の一端を垣間見せてくれるのが、「アンドロイドは電気羊の夢を見るか?」だ。
飛浩隆
SFにはツールがつきものだ。宇宙船しかり、電脳しかり、フォースしかり。それ自体が世界観を代表するようなツールが、作品に正しく個性を与える。
飛浩隆が1992年から2002年までの10年間の沈黙の後に世に送り出した中編集「象られた力」に収録されている「デュオ」のツールはピアノだ。※初出は1992年
全体、そんなありふれたツールがSF作品を代表し得るのか? お読み頂ければわかるが、これはれっきとしたSF作品に仕上がっているし、読者の想像力をふつふつと書き立て、読み終わるまで本を手放せなくなる魅力がある。
個人的に、寡作のSF作家は傑出した作品を書く人が多いように思っている。飛浩隆もそうした内の一人で、「もっとこの人の作品を読みたい!けど読めない!」というじれったさを感じる。そんな飛浩隆のTwitterには、「SF小説を書くことがあります。」とあり、自著の電子書籍版の宣伝に熱心なようだ(笑)書いてくださいよ〜。
ダニエル・キイス
SFの魅力といえば、めくるめくハードな技術描写にあるという人もいれば、そうではないという人もいる。というのも、科学技術をあくまでツール程度に抑え、作品のメッセージを重視したSF作品に少なからず名作が存在するからだ。
そうした作品は、作中に登場する科学技術のディテールを描くことには重心を置かず、むしろその技術が人々の考え方や行動をどう変えるかというところを丁寧に描く。
ダニエル・キイスは、間違いなくこの種類の作家だ。
心理学や英米文学で学位を得たダニエル・キイスをSFに引き込んだのは、「スパイダーマン」や「X-メン」を産んだアメコミ界の重鎮スタン・リーだった。未来の大SF作家は、マーベル・コミックスの前身アトラス・コミックスで編集者をやっていたのだ!
それから1959年、「アルジャーノンに花束を」でSF作家の仲間入りを果たし、いくつか著作を残しているが、最も有名なのはやはりアルジャーノンだろうか。
日本でも二回ドラマ化されて、半世紀経った今でもなお愛されているSF作品だ。
ダニエル・キイス自身はこの作品を、知識を得る過程で人間性を失うこと、周囲の愛すべき人たちとの間に壁ができてしまうことといった問題を考えるために作ったそうで、それだから、科学技術の描写が抑えられ、普段SFを読まない人でも問題なく読めて、そして泣ける作品に仕上がっているのだろう。
ただ、個人的にはゴリッゴリのハードSFも大好きです。ところが、グレッグ・イーガンが近年発表した「ゼンデギ」は、ヒューマンドラマ色が濃くなっているから残念だった。君はそっちじゃないよグレッグ!